ご存じのように、2020年10月1日に建設業法が改正され、事業承継における建設業許可の取り扱い方が大きく変更されました。大きくといっても全体としては承継に係る部分ですが。内容としては、許可を受けた業者の地位を承継できるようになったため、建設業の事業承継規制が緩和されました。それは後継者不足などの課題を解決できる一助になることが期待されています。 以下で改正後の建設業の事業承継について、その手順について述べていきたいと思います。
事業承継とは、企業や事業の経営する権利を第三者に引き継ぐことを言います。事業承継は今までにもその手段を利用してきましたが安易な承継を防ぐ狙いが行政自治体にあったと思います。
法人や事業の所有者が変わることで、経営者並びに経営自体が変わるのが一般的です。改正前と改正後の大きな違い、利点は以下になります。
改正前
業者が事業承継する場合には、承継元の会社がもっていた建設業許可を承継後の企業が引き継ぐことができませんでした。そのため、承継先の企業は建設事業をやろうとする場合には新たに建設業許可を取得することが必要でした。 具体的には、事業承継をする場合には承継前の企業で取得した建設業許可について一旦廃業届を提出し、承継後の会社で建設業許可を新たに取得する必要がありました。事業承継をする場合には承継前の企業で取得した建設業許可について廃業届を提出し、承継後の企業で新たに建設業許可を取得する必要がありました。
つまり、事業承継をする場合には承継前の会社で取得した建設業許可について廃業届を提出し、承継後の会社で新たに建設業許可を取得する必要がありました。 承継後の会社で新たに建設業許可を取得する迄の期間は、無許可状態になるため前述の建設業許可を必要とする工事を行えません。申請準備と申請後の許可が出るまでの期間は、2ヶ月程度かかります。つまり、事業承継してから4ヶ月前後も建設業許可が必要な工事や事業ができない期間が発生していました。
改正後
建設業の事業承継において、事前に認可を取得しておけば建設業許可も承継できるようになりました。 つまり、改正によって承継された会社によって新たに建設業許可を取得する必要が無くなりました。これにより、前述の建設業許可が必要な事業ができない4ヶ月の期間が発生しなくなりました。また、万が一にも事業承継した会社で建設業許可が下りない、といった不具合の発生を回避できるようになりました。
今回の改正では事業承継は建設業の衰退を防ぐ目的が大きく、承継した事業で利益を生み出しながら持続していくことが改正の主旨です。 そのためには、事業承継は 承継元の経営者の高齢化に伴う、企業や事業の存続のため、経営統合などによる、規模の拡大による経営や事業の効率向上のため 建設業全体大きな課題になっている”高齢化”への対策として打ち出されました。 建設業では、経営者を含めた就業者全体での高齢化が進んでおり、そのため、高齢を背景とした退職による就業者の減少が予想されており、経営の後継者や就業者の確保をするために事業承継が増えることが予想されています。改正業法では個人事業主が絡む事業承継における建設業許可の取り扱いが大きく変更されました。 繰り返しを恐れず申し上げるとすれば、建設業許可について、改正の前後で以下のように変わりました。 業法改正によって、事業譲渡や法人の合併や分割であっても許可番号を引き継ぐことができるようになり、最もメリットが得られたのは建設業を営む個人事業主です。 改正前には、個人事業主は建設業許可を移転することができませんでした。そのため、“法人成り”する場合でも、法人となった会社で新たに建設業許可の取得が求められました。 新たに建設業許可を取得することは、前述のとおり事業上空白期間が発生してしまう点が大きなデメリットになります。それ以外のデメリットとして、許可取得からの期間がリセットされてしまう点があります。 建設業許可番号には、許可番号を見れば、どれだけ事業年数を経過しているのかが分かるようになっています。 許可番号が古いほうが建設業を営んできたことになるため、許可番号は新しい取得年度より古い取得年度の方が好まれます。しかし、今まで建設業許可番号の承継はできなかったため、事業承継や“法人成り”や合併などの場合には許可の取り消しをしなければなりませんでした。
個人事業主が取得した建設業許可を、後継者に引き継ぐ場合には以下の方法があります。
① 法人設立 ② 個人間の事業譲渡 ③ 相続の3つの方法です。
① 法人設立
個人事業主の建設業許可を引き継ぐ最もベーシックな方法が、“法人成り”と呼ばれる法人設立になります。 事業を引き渡そうとする個人事業主が株式会社や持分会社などの法人を設立します。そして、個人事業主として取得した建設業許可を法人として承継します。その法人に、事業を引き継ごうとする人を役員などで経営に参画させます。調整のうえその法人の経営や所有を引き継ぎます。 株式会社等を設立して建設業許可をその株式会社等に引き継いでおくことで、引き継ぐ先が法人であったとしても対応が簡単になります。株式会社間であれば、事業譲渡の形で株式を譲り渡せます。形態としては、原則全部事業譲渡となるでしょう。
② 個人間の事業譲渡
事業主同士の承継は法人と異なり会社譲渡がないため、
以下のような手続きや留意点があります。
営業資産の譲渡なので個別に譲渡するかたちになります。設備や車両の譲渡契約や材料や在庫の売買、取引先の引継ぎや従業員の再雇用契約などです。このやり方も、改正前には実現できないやり方でした。その他にも税務会計の整理や金融機関の引継ぎなど留意点です。法人成りとは異なり、 この事業譲渡契約が成立した時点から、事業譲渡先の個人事業主が建設許可番号を所有・利用することができます。 ただ、個人事業主同士の事業譲渡は、法人成りには必須の会社設立の手間がかからないという利点があります。
③ 相続
相続は、建設業許可を持つ個人事業主が亡くなった場合の建設業許可の引継ぎ方法です。 改正前は、建設業許可の相続は認められていませんでした。そのため、やはり新規で建設業許可の取得が必要でした。しかし、相続に関しても法改正によって引継ぎができるようになりました。 改正前は、建設業許可の相続は認められていませんでした。そのため、やはり新規で建設業許可の取得が必要でした。しかし、相続に関して法改正によって引継ぎができるようになりました。 相続は突然に発生することもあり、建設業許可を取得していた個人が死亡などによる相続が発生した場合には、その相続の日から起算して30日以内に建設業許可の引継ぎの申請をして、引継ぎの許可を得ることができれば許可番号を相続できるようになりました。
建設業許可の事業承継手順を述べさせていただくと、建設業許可を引き継ごうとする時に、全ての手続きで共通して必要なのは事前許可の手続きになります。この事前許可が改正の重要なアイテムです。 そのため、許可を引き継ぐ上では事前認可のやり方を押さえる必要があります。事前の申請は、許可行政庁へ申請します。本店所在地ならびに営業所の所在地によって問い合わせ先は異なってきますが、大阪府や国土交通省の広報ホームページで問い合わせ先を確認できます。 事前申請から許可までの流れは以下になります。なお、大阪府知事の認可と大臣の認可へは流れも異なるので留意が必要です。
1 大阪府知事許可の場合 ①事前相談(現在、相談先は委託業者となっています) ②申請書提出(窓口審査) ③受付 ④審査 ⑤認可 ⑥通知書送付 ⑦後日提出必要資料の提出
2 大臣認可 ①地方整備局への事前相談 ②大臣認可 ③大阪府県知事への届出書提出
必要書類
- ①譲渡/合併/会社分割認可申請書 ② 相続認可申請書 ③ 役員等の一覧 ④ 営業所一覧表 ⑤ 専任技術者一覧表 ⑥ 工事経歴書(直近1年分) ⑦ 直近3年の各事業年度における工事施工金額 ⑧ 使用人数 ⑨ 誓約書 ⑩ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(該当者がいる場合のみ) ⑪ 定款(この場合公証役場での認証は要りません。) ⑫ 直近1期分の財務諸表(法人/個人) ⑬ 営業の沿革 ⑭ 所属建設業者団体 ⑮ 健康保険等の加入状況 ⑯ 健康保険等の加入状況およびその確認資料の提出に関する誓約書 ⑰ 主要取引金融機関名などとなります。
また、必要事項証明として、①常勤役員など証明書もしくは常勤役員などおよび常勤役員など直接補佐する者の証明書 ② 常勤役員などの履歴書もしくは常勤役員などの直接補佐する者の履歴書③ 専任技術者証明書 ④ 技術者要件の証明書類 ⑤ 許可申請者の住所と生年月日などに関する調書 ⑥ 建設業法施行令第3条に規定する使用人住所と生年月日などに関する調書(該当者がいる場合) ⑦ 株主や出資者に対する調書 ⑧ 発行後3ヶ月以内の登記事項証明書(法人の場合) ⑨ 事業税納税証明書
さらに、確認資料と添付資料が必要です。
- 承継方法などの書類 この書類は、事業承継(さらにその方法)と相続によって異なります。
事業承継の場合;契約書写し・株主総会議事録(株式会社の場合、持分会社は社員総会議事録)・合併の場合その詳細のわかる書面が記載された書類=合併契約書の写しおよび合併比率の説明書
相続の場合;相続では、申請者が建設業者としての地位を引き継ぐことがふさわしいかの判断をするための確認資料が必要です。 ①被相続人が死亡を証する書面、被相続人と申請者との続柄を確認できる書類(戸籍謄本や除籍謄本など)、申請者以外にも相続人がいる場合には、申請者が被相続人の建設業許可業者の地位を引き継いで建設業を営むことに対する他の相続人の同意書
② 預金残高証明書 ③『該当していない旨の登記事項証明書』等④ 破産して復権を得ていないなど該当していないことを証明するための身分証明書(発行後3ヶ月以内)(復権していれば不要) ⑤ 常勤役員などの経営経験確認資料 ⑥ 専任技術者の技術要件確認資料 ⑦ 社会保険加入状況を証明する資料 ⑧ 会社法人番号 ⑨ 営業所の所在確認できる書類 ⑩ 役員名一覧表 上記の他に後日提出する書類があります。
なかなか沢山の書類の準備が必要ですがお任せいただければこちらで準備させていただきます。
ぜひ一度ご相談ください。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


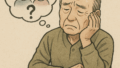
コメント